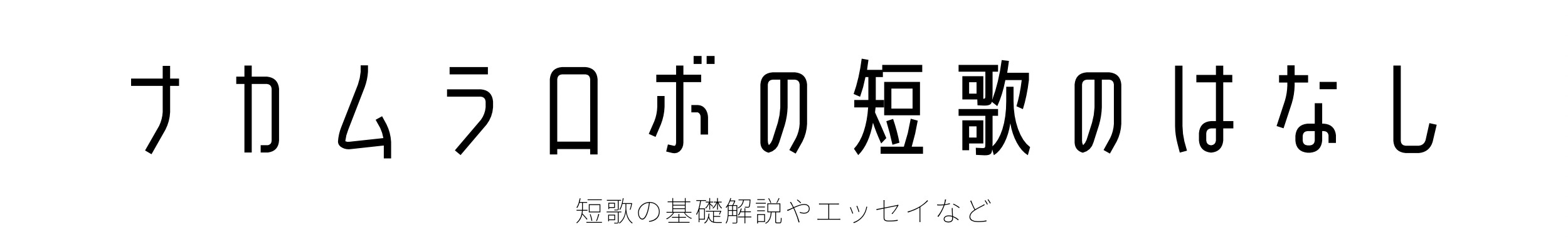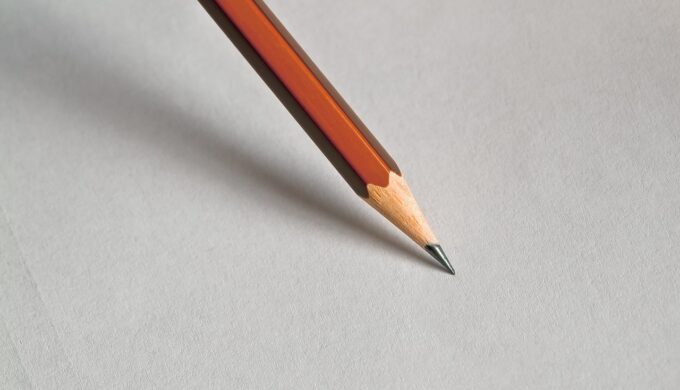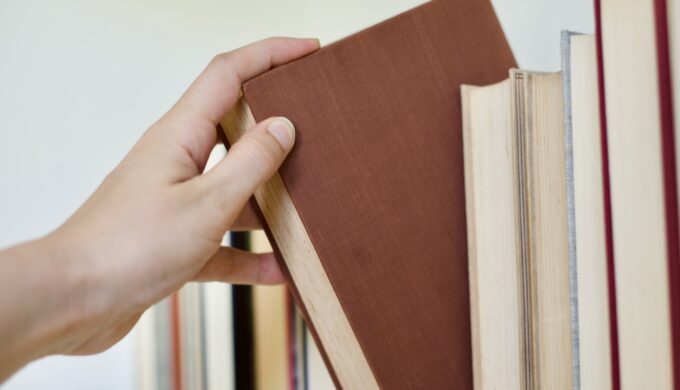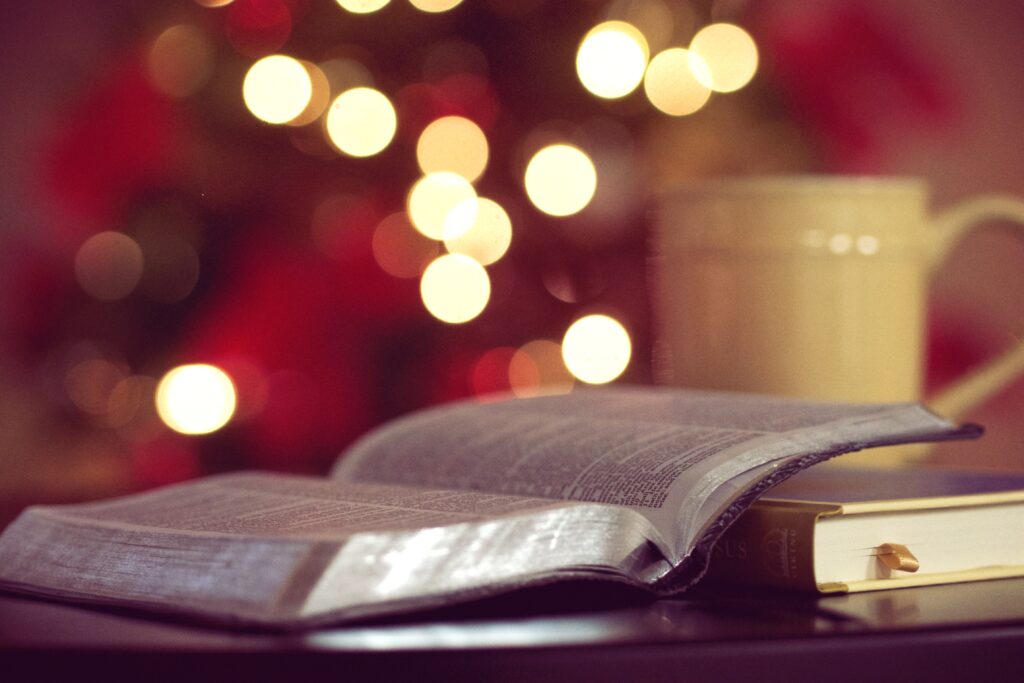
擬音語ってなに?擬態語ってなに?
短歌に使うとどんな効果があるの?
こんな疑問にお答えします。
擬音語とは
擬音語は物音や動物の鳴き声などを表した言葉をさします。
「がたがた」や「わんわん」などがそれにあたります。
これを短歌に入れることで情景をより具体的にすることができます。
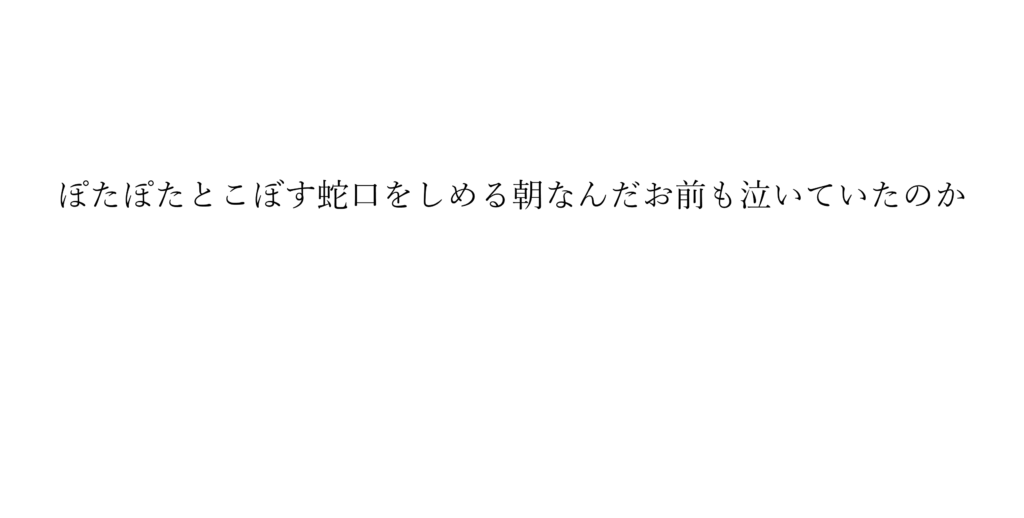
上記の歌では「ぽたぽた」が「擬音語」になります。
この歌では「ぽたぽた」で水の落ちる様子を具体的にイメージさせ、水道から落ちる水と目から落ちる涙を密接に繋げています。
擬態語とは
擬態語とは物事の見た目や様子などを表した言葉をさします。
「ぴかぴか」や「きらきら」などがこれにあたります。
これも擬音語同様、短歌に入れると情景をより具体的にすることができます。
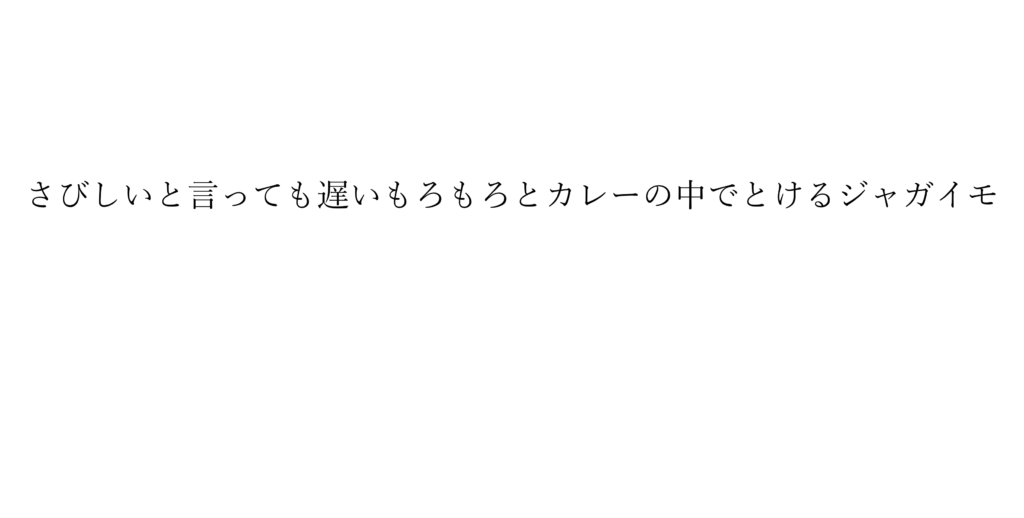
上記の歌では「もろもろ」が擬態語になります。
この歌では「もろもろ」で崩れとけていく様子を具体的にイメージさせ、崩れていくじゃがいもとさびしさで崩れていく心を密接に繋げています。
短歌における擬音語と擬態語
これまで説明したように短歌内では擬音語や擬態語は情景を具体的にし別の事象をより密接に結び付けることができます。
その他にも、意外な擬音語・擬態語を使うことで情景の印象を強めることもできます。
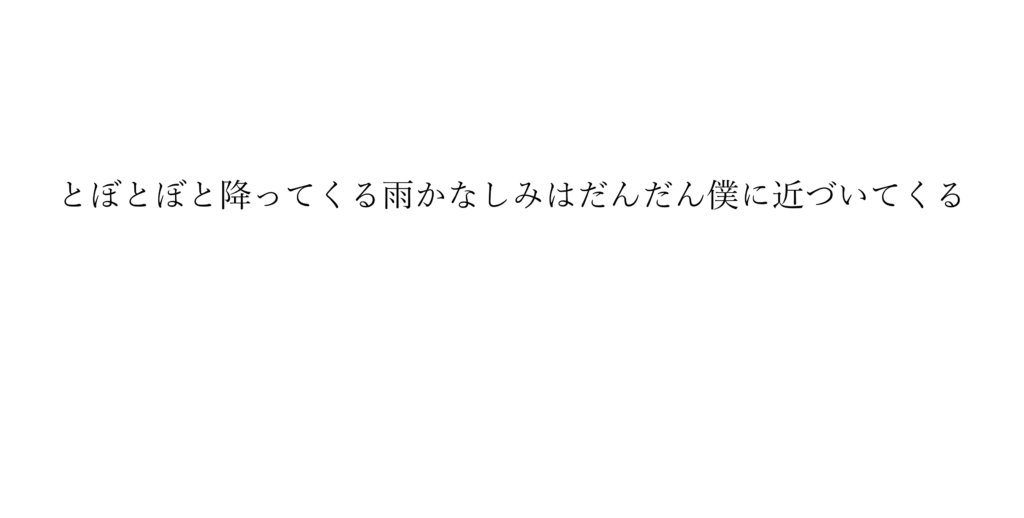
上記の歌では「とぼとぼ」が擬態語となります。本来「とぼとぼ」は「歩く」に繋がる擬態語ですが「降る」に繋げることで読者に印象付けると同時に雨自体が歩いてくるような情景をイメージさせます。
このように意外な擬音語・擬態語は使い方次第で読者に強く印象を与えることができます。そして歌人のなかには独自の擬音語・擬態語を生み出し歌を詠むひともいます。皆さんも個性あふれる表現が思い浮かんだらどんどん使ってみましょう。
本記事のまとめ
・擬音語とは「がたがた」や「わんわん」など物音や鳴き声を表した言葉
・擬態語とは「ぴかぴか」や「きらきら」など物事の様子を表した言葉
・短歌で使うことにより情景を具体的にすることができる
・意外な(あるいは独自の)擬音語・擬態語を使うことで歌の印象を強くできる